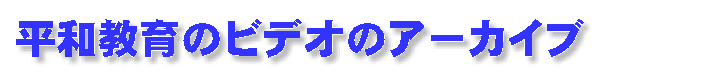 2025年7月29日更新
2025年7月29日更新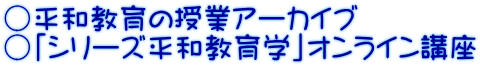 リンク
リンク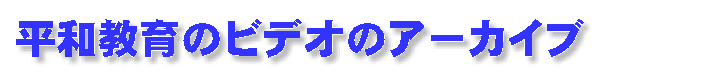 2025年7月29日更新
2025年7月29日更新
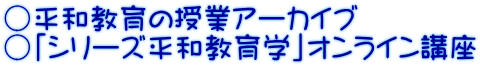 リンク
リンク

| 平和教育を実践できる教員の養成に向けて、平和教育のための講座を、「シリーズ平和教育学」としてオンラインで2023年度より公開し、受講者の平和教育実践と研究をサポートします。「シリーズ平和教育学」では、子どもたちに主体的で創造的な学習を促す視点から、視聴者が学習内容をデザインし実践する力を高めることを目指します。 | ||
| 日程 テーマ | 解説ビデオ(You Tube) リンク | 概要 |
| 2023年 7月7日 平和教育学の理論 |
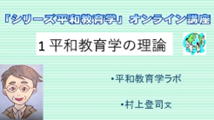 |
【平和教育の理論を見ていきましょう】 平和教育学では、平和教育の理論と実践について研究し、アカデミックな立場から、学問的知見を体系化していく。平和教育学の研究法、平和教育の理論や概念の分類、平和教育の実施の場、これからの平和教育の方向性について説明する。 |
| 7月14日 平和教育学の歴史 |
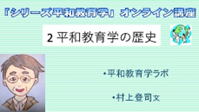 |
【年代によって平和教育が変わっていきます】 戦後日本の平和教育がどのように展開してきたか。平和教育が、一般の人々によって、また公的機関により、どのような公的支援を受けてきたのか。平和教育実践を推進した要因、および抑制した要因の観点から、平和教育が展開する歴史を鳥瞰し、平和教育を進めていく仕組みについて考える。 |
| 7月21日 子どもの平和意識 |
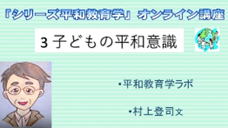 |
【中学生に対する平和意識調査から戦争や平和についての意識の作られ方は】 実証的検証による研究成果として、子どもの平和意識について説明する。中学生が日本や世界を平和と思っているか、正義の戦争論を認めるか、戦争をしない平和主義に対する意見を時系列的に、また4カ国での調査結果を比較分析する。平和な社会の形成への参加意欲や貢献方法について分析し、日本の平和教育の特性について説明する。 |
| 7月28日 平和教育への問と回答例 |
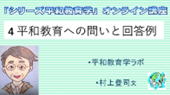 |
【平和教育への視聴者からの課題】 平和教育への14の問いとそれへの回答例を示している。問いの例としては、平和について自分事として考え行動する力を培う方法は何か。平和教育の構造は何で、どのようにつくられるのか。平和教育関係の学会同士が、垣根を越えて研究や実践を進める方法は何か、等が出され、それへの回答例を説明する。 |
| 2024年 1月12日 次世代による戦争体験の継承 |
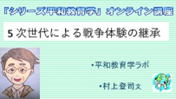 |
【学習方法の工夫について説明します】 戦争体験の継承が、体験者を父母とする戦争体験第2世代と、体験者を祖父母とする第3世代(合わせて次世代)によって行われ、現在は平和教育の過渡期にある。78年前の戦争を伝えるためには、学習方法の工夫により、今起きている戦争の学習に繋げていく。戦争体験の継承活動を若手教員や子どもたちが担うためには、活動に参加する当事者意識を高めるプロセスを必要とする。 |
| 1月19日 平和教育のカリキュラム |
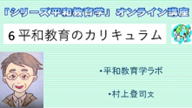 |
【平和教育の内容の作り方を考えてみましょう】 日本の平和教育は、 第二次世界大戦での戦争被害体験の題材を、多く扱っていた。広島・長崎の被爆体験や、沖縄の地上戦体験、都市への空襲体験を学ぶだけでなく、平和を創ることを学ぶのも必要である。平和教育実践のマンネリ化や形骸化を防ぎ、子どもが興味・関心を持って学べるように、発達段階に応じて学習目的を系統化し、平和教育カリキュラムを作成することが必要である。 |
| 1月26日 ドイツの平和教育 |
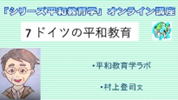 |
【戦争加害と平和構築を視座に入れた平和教育の実践してきたドイツ】 ドイツは第二次世界大戦前にはファシズムが支配し、大戦中に周辺国を侵略し、敗戦で国民は大きな戦争被害を受けた。ドイツでは青少年への政治教育を重視し、ナチス政権下の政治的な弾圧状況や、周辺国への戦争加害を詳しく教えている。日独の中学生に対する平和意識調査の比較や、戦跡資料館の展示内容や教育機能について比較検討し、戦争と平和を多角的に見る視点を修得する。 |
| 2024年 7月5日 地方自治体による平和啓発と学校の協同 |
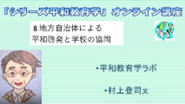 |
【地方自治体の平和啓発事業と学校教育が協同することができます】 全国のほとんどの自治体が非核宣言(2024年に93.2%)をしている。被爆地の広島や長崎、地上戦のあった沖縄は、平和政策や平和事業において特に熱心である。地方自治体の平和啓発事業と学校教育とが協同する関係には、開催型、募集型、派遣型、支援型がある。多様な自治体の平和啓発事業が、学校での平和教育実践を地域社会に定着させる現状について考える。 |
| 7月12日 昔と今の平和教育者 |
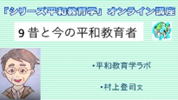 |
【平和教育を実践する人、平和教育者を増やすには、どのようにすればよいかな】 日本の平和教育は、 第二次大戦の戦争被害体験である広島・長崎の被爆体験や、沖縄の地上戦体験、都市への空襲体験を学ぶだけでなく、平和を創ることも教えてきた。被爆教師は、広島や長崎での被爆体験を通じて平和教育に取り組み、平和の大切さを伝える平和教育者の存在であり、平和教育の礎となった。平和教育者たちが、今までどのように形成され、何をなし、どこに向かうかを考える。 |
| 7月19日 公的な支援・支持 |
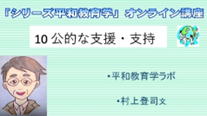 |
【平和教育を公的に支持するものは何でしょうか】 平和教育の推進を、公的に確認し、その発展を推し進める「公的支持」は何かを考察する。平和教育に対する公的支持を5つの分野(研究、実践、法規、政策、行事)から分析する。実践分野での平和教育の発展は戦後すぐにあり、研究分野はそれの後追いで発展する。平和教育が、歴史的に展開する過程を俯瞰し、何が平和教育を推進し、何が抑制してきたかを考える。 |
| 2025年 1月17日 平和教育の今日的課題 |
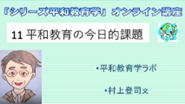 |
今の平和問題を、子どもたちにどのように教えれば良いのでしょうか。日本の平和教育においては、80年前の沖縄戦や広島・長崎で原爆などの戦争経験について話を聞くことが主流になってきました。しかし、戦争を語れる方も高齢化し不在化が進んでいます。他方で、ウクライナ戦争やイスラエル・ガザ戦争は現在も進行しています。古きに学び、新しい状況に対応する平和教育実践をつくらなければならなりません。昔の日本の戦争を、今起こっている平和問題に、平和学習でどう繋ぐのか探ります。 |
| 1月24日 平和教育の授業づくり |
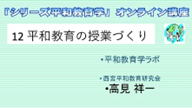 |
2025年は第二次世界大戦後80年目となります。平和教育において日本の戦争体験の継承は、最重要な学習課題です。しかし、子どもたちの多くは、第二次大戦の戦争体験を自分たちにはあまり関係のない昔話や思い出話としてしか聞いていません。そうした今の時代状況において、「戦争を知らない教師」たちは、平和教育をどのように行えば良いのでしょうか。 「平和教育の授業づくり」のHPを参考にして、平和教育の実践方法を、高見祥一さんが解説します。 |